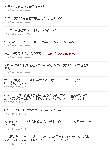「だってペットが死んでこんなに悲しいなら親だったらどうなるの」
まるで人の隙間にこぼれ落ちたみたいなその言葉はやけに教室に響いて
その瞬間いくつもの視線がこちらを向いた
気がした。
さよならいつか
救急箱から絆創膏を取り出して、膝頭と頬にペタリ。鼻は・・・まあいいか。ちょっと赤むけてるけど、大して擦ってもいないし。
今日の授業の最後は体育。しかも野球だったから、締めくくりとしては悪くない。久々の紅白戦は白熱して、紅組の最終打者(俺だ)のヘッドスライディングが勝敗を分けた。結果はもちろん紅組の勝ち。
ちょっと前みたいにケンカで傷だらけになることは少なくなったけど、だからって絆創膏がいらなくなる訳じゃない。この前兄貴が特売で買ってきてくれたばかりなのに早くも底が見えかけているお徳用パックの箱を救急箱に戻し、いつも通り薬瓶の中身を確認して、それに気がついた。
風邪薬が減っている。
この家には2人しかいないから、俺じゃないなら飲んだのは当然兄貴だ。9月の連休が終わった途端、肌寒い日と冷たい雨(秋の長雨というらしい)が続くようになって、体調を崩してしまったんだろうか。
兄貴は決して病弱という訳ではないけど、季節の変わり目にはちょっと弱い。昔は─それこそ母さんが生きてた頃は─ちょくちょく寝込んでたりもしたけれど、最近ではそうなる前に薬を飲んでさっさと治してしまうのが普通だったから、風邪で学校を休むような事は滅多になかった。
気を張っているんだ、という事は、子供心にも解っていた。
だから、兄貴が絆創膏の減り具合をチェックしてるように、薬瓶の中身を見るのは俺の(秘かな)役目だと思っていた。あまり表立って気にかけると却って気を遣うような人だから、あくまでもさりげなく。少しでも余計な負担をかけないように、できるならいざという時に少しでも兄貴を助けられるように。
そう、思っていたのに。
「おかえり、兄ちゃん」
学校帰りに買物を済ませ、制服姿のままで袋の中身を冷蔵庫に仕舞っていた兄貴に、背後から声をかける。
「ただいま。─また派手にやったなあ」
絆創膏だらけの俺の顔を一目見るなり、兄貴は呆れたように笑った。
「野球、ついマジんなっちゃってさ」
「当然勝ったに決まってるよな?」
「当然勝ったに決まってんじゃん」
そんな風に軽口を叩きながら、買い物袋から野菜を取り出して兄貴に渡す。それまでは買物も二人で一緒に行くことが多かったけど、この年の春から中学校と小学校に分かれて以来、兄貴が一人で済ませる事が多くなっていた。
さっき見た薬瓶の事もあって、つい確認するように兄貴の顔ばかりちらちら見ていると、
「なに?」
と、兄貴の方から声を掛けられた。しまったと思ったけど、自然にさりげなくと思えば思うほど俺の態度はぎこちなくなってしまい、ついには顔を覗きこまれて「具合でも悪い?」と真逆の質問をされてしまう。
慌ててふるふると頭を振り、何か違う事を、と話題を探した。
「ウチのクラスの女子がさ、飼ってたペットが死んじゃって」
・・・咄嗟に振った話題としては、ハッキリ失敗だったと思う。けど、こういう話題こそ食い付いてくるのがうちの兄貴なんだよな。
「ペット?犬?猫?うさぎ?」
ホラやっぱり食い付いた。
「何だったかな。名前はマルとか云ってたけど」
「それじゃ何か判らないな」
自分で云い出しちゃった事だし、仕方なく俺は話を続ける。
「そのマルがさ、一年生の時に拾ったヤツだったんだって。で、飼う時も結構反対されたらしいんだけど、今になって反対された理由が解ったって」
「?」
「こんなに辛いなら飼わなきゃ良かったって」
「・・・ああ」
ダメだよそんな事云っちゃ。マルだって可哀想だよって、周りの女子が慰めてる中で、その言葉は隙間にすこんと落ちたパチンコ玉みたいに響いた。
「だってペットが死んでこんなに悲しいなら親だったらどうなるの」
その瞬間、みんなの目が一斉にこちらを向いたと思ったのは、気のせいじゃなかったと思う。
今時、親が離婚してたりして片親の家庭なんて珍しくないし、うちのクラスにも数人いる。けど、不仲でもない両親を一度に亡くしている家庭はうちだけだった筈だ。
「あ・・・」
短いけど鋭い氷柱みたいな沈黙は、それを作り出した本人の口で破られた。
「ごっ・・・ごめ・・・そういう、つもりじゃ・・・」
『そういう』がどういうものかはわからないけど、とにかく取り返しのつかない事を云ってしまった、という事は判るんだろう。さっきまでは顔を真赤にして泣きじゃくってたのに、今は青ざめて唇が震えていた。
「ペットが死んじゃった事は無いけど、悲しいのは同じなんじゃないの」
別に助け舟のつもりじゃなかったけど、俺がそう云うとその女子は『ごめん』とまた謝って、そして始業のチャイムが鳴った。
「兄ちゃんもそう思う?」
もちろん『親が死んだら』云々の部分は云わずに、訊いてみたかった事だけを問う。
悲しい思いをするなら拾わなければ良かったのにって、兄ちゃんもやっぱりそう思う?
兄貴は決して思いつきで物を云わない。いつものように、考え事をする時の癖で口に手を当てて、少しだけ黙り込んだ後で口を開いた。
「俺は・・・」
けれどその途端、立て続けに咳き込んで言葉はかき消された。
「に・・・っ兄ちゃん!」
慌てて背中をさすると、しばらくして『大丈夫』と云うように兄貴の左手が上がった。
「えと、続きは俺やっとくから着替えてきなよ。晩ごはん何?皮むきくらいなら俺できるし」
声が震えないようにしたら早口になってしまった。そんな俺の不自然さにも気付いてるだろうに、兄貴は呼吸を整えると、涙の溜まった目で俺に笑いかけた。
「・・・そうだな、玉ねぎ剥いておいてくれるか?着替えてくるよ」
「おう!任せとけ!」
選手交代。ハイタッチのつもりで体温を探る。熱はないみたいだけど、顔色は確かに良くない。
ソファに置いてあった学生鞄を持って部屋に向かう兄貴を見送って、俺はありったけの雑言を自分にぶつける。俺の大バカ。マヌケ野郎。さっさと休ませれば良かったのに、変な話題振って長引かせて。
ひとしきり悪態をつきながら、頭の中はぐるぐる回る言葉で溢れ返りそうになっていた。
『だってペットが死んでこんなに悲しいなら親だったらどうなるの』
もしも兄貴、だったら。
翌朝。兄貴はいつも通り早起きして、いつも通り朝ごはんを作って、いつも通り俺を起こしにきた。いつもと違ったのは、その時俺はもう起きてて、着替えを済ませてた事くらい。
「珍しいな。どうしたんだ?」
いつもなら布団を引っぺがされるまで起きない俺だから驚くのも無理はないけど、本気で心配そうに見るのは止めてほしい・・・。いや、日頃の行いが悪いのがいけないんだけどさ。
ホントは兄貴が隣で布団を畳みだした時も起きてたんだけど、さすがに早起きし過ぎかと思って、これでも頭使ったんだよ。一応。
「別に、たまたま目が覚めちゃっただけ。それより今日なんか帰りに買う物ある?」
「うーん、昨日大体買ったしなー。・・・あ、洗面所の電球。切れかけてた」
「じゃ、俺それ買ってくる」
お遣いを引き受けて、朝ごはんを片付けて、二人で揃って家を出る。「今日はいつもよりのんびりできたな」なんて云われてちょっと嬉しかった。少しは楽になれたかな。
中学校の方が小学校より家から近いし、鍵は俺も持ってるから、本当は兄貴はもう少しのんびりしてても良いんだけど、『二人一緒』にこだわったのは兄貴の方だった。
始業式も近い春休み中のある日。今度から一人でガッコ行くんだよなーなんて軽く云った俺に、兄貴は一瞬驚いたような顔をして、それから覗きこむように俺を見た。
『どうせ帰りはバラバラになるんだからさ。朝くらい一緒に行こ?』
そんな風に云われて、嫌だなんて云えるはずもない。(云うつもりもなかったけど)
もちろん一緒に家を出たってそんなに長くは並んでいられないけど、来年は俺も中学だし、そしたらまた帰りも一緒にいられる。それだけで、俺は来年の春が楽しみで仕方がなかった。
「じゃあな、行ってらっしゃい。気をつけろよ」
「兄ちゃんも。行ってらっしゃい!」
十字路でお互いに手を振って別れる。しばらく歩いていたら、ふと忘れものに気が付いた。
(しまった。洗面所の電球)
これと同じものだからな、と兄貴がわざわざ商品名やワット数を書いてくれたメモを、しっかり玄関に忘れてきてしまった。まあいいか、同じようなのを買ってくればと思ったけど、前にもそれで全く違う物を買ってしまって、結局ワット数が合わずにレシートを持って交換しに行った前科がある。
どうやらまた同じパターンになりそうだと思った俺は、さっさと道を引き返した。まださっき別れたばかりだし、追いかけてもう一度聞こう。
十字路を曲がると、すぐ兄貴の姿を見つけた。声を掛けようとして、けれど一人じゃないのに気付いてためらっている内に、その会話が耳に入る。
正確には、兄貴を挟むようにして、両脇の二人が交互に云い立てていた。
「・・・つーかさ、いい加減医者行けよ。なんか酷くなってんじゃん咳」
「もう一週間近くなんじゃね?保健室の薬、マジ効かねって」
「常連になると担任うっせーぞ」
一週間?
保健室?
常連って、どういう事?
「すぐ治ると思ったんだよ。病院行くと弟が心配するし」
「ちっとも治んねー方がよっぽど心配だっつの。それくらい内緒で行ってこいよ。ってか、お前弟甘やかしすぎ」
「だなー。俺から云ってやろうか」
「何を?」
「お前んトコの兄ちゃん、このまんまじゃぶっ倒れるぞって」
「絶対止めろ」
低い声で云いながら睨みつけて、でもすぐにまた咳き込んだ兄貴を、ああもうわかったわかったなんて宥めながら両脇の二人が背中をさする。
俺は踵を返して来た道を走り出した。
知らなかった。
知らなかった。
知らなかった。
何を?兄貴の咳がもっとずっと前からだった事。俺が全然それに気付いてなかった事。気を遣うとか助けるとか、そんなのが全部俺の自己満足だった事。
兄貴に、あんな近い友達がいた事。
兄貴は所構わず独り言を云ったり考え事に没頭する癖があったから、小学校では少し浮いた存在だった。表立っていじめられてこそいなかったけれど、すごく親しい友達もいないように見えて、だから兄貴は俺と遊ぶことが多かったし、学校が終わって真っ直ぐ家に帰ってくるのも特に違和感は覚えなかった。それどころか、兄貴には俺しかいないんだって優越感すら持っていた気がする。
けれど、ほんとは違ったんだろうか。
兄貴はとっくに俺を卒業してて、けど俺がまだガキだから仕方なく付き合ってたんだろうか。ほんとは友達と遊んだり部活をしたり、もっと色々な事がしたかったのに、そんなのを全部我慢して家に帰ってきてくれてたんだろうか。
初めて中学の制服を着た兄貴を見たとき、カッコいいよなんて茶化しながら、本当はとても嫌だったのを思い出す。その時はどうしてか判らなかったけど、今なら解る。兄貴が知らない人みたいに見えたからだ。今まで何をするにも二人一緒だったのに、急に置いてけぼりにされるようで怖かったからだ。
『だってこんなに悲しいなんて思わなかった』
昨日聞いたあの言葉が回る。ねえ、知ってたらどうだったの?好きになんかならなかった?先にいなくなるって、いつか必ずさよならの日はくるって、父さんと母さんみたいに、俺を置いて、いつか必ず、そうだよいつか、兄貴だって
「・・・嫌だ」
自分の声に、はっと我に返る。いつの間にか小学校の門の前だった。
なんだ珍しく早いななんて先生の言葉も無視して教室に走った。
『兄ちゃんもそう思う?』
あの時、兄貴は何て答えようとしたんだろう。
それから二日間、俺は兄貴を避けた。
表面上はいつもと変わらないけど、登下校やら食事やら、何かと理由をつけては二人きりになるのを避けまくった。
と云っても元々二人しか住んでいない家で、それは思った以上にキツかったし、逆に今までどれだけベッタリ過ごしていたのかを再確認する結果になった。
けど、いつまでもそんな風に過ごせる訳がない。三日目にとうとう、兄貴がキレた。
「・・・潤也、何か俺に云いたいこと無いか?」
さすがに毎日帰りが遅いのをとがめて、晩ごはんの席で兄貴が云った。
「別に、何もないよ?」
内心、ビクビクしていた。俺は嘘が下手なのは自覚してたからなるべく向かい合わずにいようと思ったのに、こうして正面に座ると、兄貴の目は恐ろしいくらいに澄んでいて、やましい俺はあっさりと目を逸らしてしまう。
兄貴の向こうにあるキッチンの壁なんかを見ながらとぼけると、
「・・・そっか」
もっと何か云われると思っていたのに、あっけなく兄貴は席を立ち、自分の皿を持ってシンクに向かった。
洗い物の音が響く中、もそもそと一人でご飯を食べながら、俺はいつまでこうしているんだろう、と自問する。
いつになったら平気になれるんだろう。
大人になったら平気になるんだろうか。
大人になるまで一人でいるんだろうか。
一人でいたら大人になれるんだろうか。
「潤也」
不意に呼びかけられて、跳ねるように顔を上げる。
あかい瞳が真っ直ぐに俺を見て、そして。
「俺達、いつまでこうしていられるんだろうな」
─まるで俺の心を読んだような、けれど少し意味合いの違いそうな言葉に、何か云おうとして言葉が出てこない。ほんのちょっと前まで、あんなにも簡単に出てきてた言葉が、何一つ。
逃げ出したい。けれどずっと見ていたい。矛盾する気持ちを飼い慣らすことも出来ないまま、俺はそっと視線を外した。
「・・・おやすみ、潤也」
消灯ですよ、とは云われなかった。
「いってきます」
翌朝。どんよりとした曇り空の下、俺はその日も一人で家を出た。
傘を持って出なかったのは失敗だったかも知れない。曇っているせいか、空気もいつもより肌寒く感じる。兄貴の風邪は治っただろうか。鞄の隙間からちらっとだけ薬局の薬袋が見えたから、病院には行ったみたいだったけど。
一昨日の夜以来、兄貴は隣の部屋で寝るようになっていた。「うつしたらいけないから」という言葉が、言葉通りのものなのかそうでないのかは、兄貴の顔すらまともに見られない俺には判らなかった。
雨が降り出したのは、授業が終わってすぐだった。結構な大粒を落す空を恨みがましく見上げると、これからウチに遊びに来ないか、と後ろの席の奴に声を掛けられる。
「あ、でも兄ちゃんが心配するっけ」
そう云われて、いつもならゴメンと手を合わせる所だけど、この日の俺には渡りに舟だった。俺は、学校から歩いて2分の団地に住んでる癖に、しっかり傘を持ってるそいつの家に向かった。
「ただいまー」
「おかえり。─あら、いらっしゃい潤也君」
「お邪魔します」
居間でテレビを観ていたおばさんに挨拶をすると、
「直接来るなんて珍しいのね。お兄ちゃんには云ってあるの?」
目敏いおばさんは、俺のランドセルを見てそう云った。いつもなら必ず、家に一度帰って鞄を置いてから来るようにしていたから、単純に不思議に思ったんだろう。ハイともイイエとも答えられないでいると、
「潤也、今日傘無いんだよ」
だから雨宿りな、と俺に代わって答えてくれた奴に感謝して、俺達は部屋に向かった。
「やっと止んだな、雨」
そんな呟きが聞こえて、ゲーム画面から目を離してそちらを見ると、真っ暗な窓の向こう側はシャワーで洗ったみたいになっていた。さっきまで網戸をバチバチ鳴らす程だった雨音もすっかり静かになっている。時計を見ると、もうすぐ6時半になるところ。
「そろそろ帰るだろ。兄ちゃん心配してるだろうし」
その時、廊下で電話が鳴った。
なんとなく予感があったのか、俺と奴は自然に目を合わせると、しばらくしてコンコンとノックの音が響いた。
ドアを開けるとおばさんが立っていた。
「潤也君。お兄ちゃんから電話」
はい、と電話の子機を差し出される。俺は一瞬だけそれを見るけど、受け取ることはできないでいた。
しばらくして、口を衝いて出たのは
「・・・もう帰ったって云って」
「潤也君?」
「潤也?」
「金曜日だし、今日泊めてもらえないかな・・・お願いします」
最後の言葉はおばさんに向けたものだ。おばさんは俺の顔を見て小さく溜息を吐くと、子機の保留を解除した。
「あ、お兄ちゃん?ごめんなさいねぇ。潤也君、すぐに帰るから。・・・ええ、心配掛けてごめんなさいって」
おばさんはそう云うと、子機の電源を切った。
「なんで!」
自分勝手なのは判ってる。けど、どうしても堪え切れない理不尽な思いがぐるぐる回っていて、思わず大声を出した俺に、おばさんは目線を合わせて云った。
「お兄ちゃんとケンカした?」
首を振る。違う。こんなの全然ケンカじゃない。
「お兄ちゃんが嫌いになった?」
これも首を振る。嫌いじゃない。嫌いになれる訳がない。
「だったら、ちゃんとそう云わなきゃ駄目」
・・・云える訳もない。だからこんなに苦しいのに。
何を云われても首を振るしかない俺に、おばさんは「あなた達にはまだ判らないだろうけど」と云った。
「誰かと一緒にいられる時間って、ほんとはすごく短いのよ」
その言葉に、俺は顔を上げた。
『俺達、いつまでこうしていられるんだろうな』
兄貴の言葉が耳に返ってくる。あの時、兄貴はどんな顔をしていたんだろう。怒ってた?泣いてた?悲しんでた?
違う、と思った。
あの時、兄貴は苦しんでた。
俺なんかより、もっともっと。
「・・・俺、帰る」
「そう、じゃあ送って行くわね」
「いい!」
俺はランドセルを引っ掴むと、玄関に向かって駆け出した。
「ごめんなさい、ありがとう、お邪魔しました!」
まとめて全部云って走り出すと「また月曜日なー」という声と「気をつけて」という声が背中で聞こえた。
俺はもう一度振り返って頭を下げると、今度こそ全力で走り出す。
兄貴が突然いなくなるという想像にすっかり俺は怖気づいて、これ以上好きになるのをやめようと思った。だって俺は兄貴がいたから、父さんと母さんが死んでもまともな生活に戻れたのに、その兄貴がいなくなったら?どうやったってあんな事、もう一度越えられる自信なんてない。兄貴がいないのに、たった一人でなんて。
だから、もうこれ以上好きになんかなんない。一人に慣れるんだ。いつか兄貴がいなくなっても大丈夫なように。
兄貴には友達もいるし、俺がいなくたってきっとちゃんとやっていける。それどころか、邪魔な荷物が無くなったら、もっと自由に好きな事をやれるようになるかもしれない。
けど、ごめん、兄貴。
やっぱり俺は駄目だよ。
だって兄貴しかいないんだ。
俺にはもう兄貴しかいないんだ。
家に帰ると、部屋の灯りは点いていなかった。
もしかして出掛けてるんだろうか、とドアノブに手を掛けると、予想に反して扉はすんなりと開いた。
「・・・ただいま・・・」
真っ暗な廊下は静まり返っていて、人の気配もない。玄関の電気を点けると、たたきに兄貴のスニーカーと傘が転がっていた。
まさに『転がっていた』としか表現できないほど、無造作に脱ぎ捨てられたスニーカーと傘はどちらもぐっしょり濡れていて、もしかしたら俺を探していたんだろうかと思い当たる。
それを裏付けるように、階段下にはやっぱりびしょ濡れになった兄貴の鞄と俺の傘が、投げ捨てられたように一緒に落ちていた。
今度こそ、怒ってるのかも知れない。
らしくなく脱ぎ散らかされた靴や、灯りも点けていない家が、拒絶を証明しているようで怖かった。けれど、このまま兄貴に見捨てられる事はもっともっと何倍も怖かったから、俺は勇気を出して二階に上がった。
「兄ちゃん・・・入っていい?」
普段はした事もないノックをしてから声を掛ける。何も聞こえてこない返事に、いっそドア越しに謝ろうかと思ったけど、それでは謝った事にならないからと、意を決してドアを開けた。
灯りを点けて、眩しさに目を細める。
けれど。
「にい・・・ちゃん?」
部屋には誰も居なかった。
布団が敷かれている訳でもなく、朝家を出た時のままだ。
最近、兄貴が寝ている隣の部屋のドアも開けてみる。が、やはりこちらも空だった。
「兄ちゃん・・・どこ?」
じわりと、黒い染みのように滲み出す恐怖。
背筋をすうっと冷たい汗が流れ落ちる。
兄貴はずっと咳き込んでいた。
なのに俺を探していた。多分、あのひどい雨の中を。
違う。ひどい雨だからこそ、だ。
びしょ濡れの靴に、傘。階段下の鞄。
あれは放り出されたんじゃなくもしかして
それだけの余裕、すら
「・・・兄ちゃん!」
階段を駆け降りると、一番近い洗面所、トイレ、風呂場とドアを開けて行く。最後にリビングの電気を点けて、けれどそこにも人の姿が無いのを確認すると、焦りと後悔で息が詰まりそうになった。
頭のどこかが真っ白になっている。心臓がおかしな具合に跳ねて、喉が震えて息がし辛い。何かがカチカチという音がして、うるさいなと思ったら自分の歯が鳴っていた。
どうしよう。ごめんなさい。にいちゃん。ちがうんだ。きらいなんかじゃ。どうしよう。どうしたら。どこにいるの。にいちゃん。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
『誰かと一緒にいられる時間って、ほんとはすごく短いのよ』
ばかだった。いつ来るかもわからない「いつか」に一人で怯えて、兄貴の気持ちも何にも考えないで。
二度と会えなくなるのがどういう事かって、そんな事とっくにわかってたはずなのに。
もう一度二階を探そうとして、それに気づく。
キッチンに続く扉の陰から覗く、床の上に放り出された、白い
人形みたいな
腕 が
「兄ちゃん!!」
それから先の事はあまり覚えていない。気がついたら病院の廊下で、隣にはさっき別れたおばさんがいた。
あの後、俺からかかってきた電話は完全にパニクっていて、慌てて車を飛ばしてくれたおばさんが、キッチンで倒れている兄貴と、兄貴を抱えて泣き叫んでる俺を見つけて救急病院に連れて行ってくれた。らしい。後で聞いた話。
診断結果は肺炎だった。もう少し遅かったら危なかったという話を聞いて、俺はまた鼻水だらけになりながら泣いた。あんなに泣いたのは、父さんと母さんが亡くなった時以来だったと思う。
「ごめんな、潤也」
病室で目を覚ました兄貴が開口一番、口にしたのはそんな言葉だった。
「なっでっにいちゃ、あやまっ、わる、の、おれ、でっ」
・・・人間って、泣きすぎると最終的には脳からも塩分が出るんだと思う。ぐずぐずに崩壊しまくって云ってる本人にも何が何だかわかんなくなってる言葉を、それでも兄貴は正確に理解してくれた。
「うん、潤也も悪いよ」
あっさり云われてまたえずくように泣き出した俺の顔を、兄貴がほらほらとティッシュで拭いてくれる。
「珍しく何か悩んでるな、とは思ったんだけど、いつか云い出してくれると思ったんだよな。なのにいつまでも一人で悩んでて、最後には無視されるし」
冗談めかした云い方だけど、熱は大分引いたとはいえまだ胸は痛いらしい。ゆっくりゆっくりと喋る兄貴に『もういいよ』って云おうとしたら、一瞬先に止められた。
「でも、待ってちゃいけなかったんだよな」
顔を上げると、優しく細められたあかい瞳が目の前にあった。
「前に云ってただろ。ペットが死んだ子の話。拾うべきじゃなかったのかって」
「う、うん」
「最後に別れることが判ってるからって、一緒に過ごした日が無駄になる訳じゃないよな」
くしゃりと髪を撫でられる。少しだけ久し振りな、大好きな仕草。
「大事なのはさ、その日に後悔しない事だと思うよ。だから、毎日無駄にしないように生きていかなきゃならないんだよ」
─俺達、いつまでこうしていられるんだろうな─
兄貴は知っていた。俺の、悩みとも云えないような悩みの理由も、それに対する答えも。
きっと、兄貴は俺よりもずっと早くそれにぶち当たっていたんだ。そして苦しんだ。そう多分きっと、あの八月に。
そうして兄貴がたった一人で出した答えが何だったのか。俺にだってもうわかる。
だってそれこそが、二人で暮らした今日までの日々、そのものなんだから。
「にいちゃん」
「ん?」
「ごめんね」
「俺も、ごめんな」
いつかさよならする日は来るけれど。それは絶対に避けられないけれど。
いつか来るその時に、後悔しないように。
「にいちゃん」
「なに?」
「だいすき」
「俺もだよ」
俺達は生きていく。
END
潤也視点の話は一応回想という形を取っていますので、
台詞は「兄ちゃん」、地の文は「兄貴」です。
その割に現在進行形の部分もあったり、やけに大人びた
云い回しがあったりするので、もしかしたら違和感がある
かもしれません。が、そこはそれ、管理人の表現力の
及ばないところだと思って諦めて下さい・・・。
ほぼ同名タイトルの某小説とは当然全く無関係ですが、
結構古いし大丈夫よね~なんて思ってたら、まさに今日、
くだんの小説の「来年映画公開」の報を知って吹きました。
なんてタイミング。これもセレンディピティのなせる業か。
ただの偶然です。(わかる)
しかし今更他のタイトルも思いつかないので決行です・・・。
万が一検索でたどり着かれた方がいらしたらすみません。
ってここまで読まれるとは思えませんが。
(読まれたら読まれたでそれもまた(大汗))